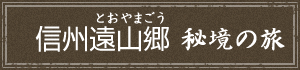秋葉街道
秋葉街道~秋葉以前の遠信古道~
秋葉街道は、秋葉信仰が広まるよりも前から存在していた古い道です。柳田国男はこの道について、「我々から言うならば寧ろ諏訪路とも、遠山通りとも呼んでみたい」と述べています(「東国古道記」)
縄文時代からの塩の道
この遠信古道―のちの秋葉街道―よって運ばれていた重要な産物の一つに、塩があります。
海のない信州に持ち込まれる塩は、日本海からの「北塩」と、太平洋からの「南塩」がありました。南塩ルートの主なものには、遠州からの遠信古道と、三河からの中馬街道の二つがあります。中馬街道の成立が戦国時代以降であるのに対して、遠信古道の誕生は古く先史時代に溯ります。
遠信古道は、遠州灘の相良から発して遠山地方を経て諏訪湖に続いています。南信濃村から出土する縄文時代の遺物からも、北は諏訪和田峠、南は東海地方との交通が窺えます。当時、遠州からは塩、信州からは和田峠の黒耀石などが運ばれ、遠山谷を行き交っていたことでしょう。
昭和十七年まで、秋葉寺の火祭りの際には湯立て神楽が行われていました。その湯に塩水が用いられていたという事実も、秋葉街道と塩との関わりの深さを物語っているようです。
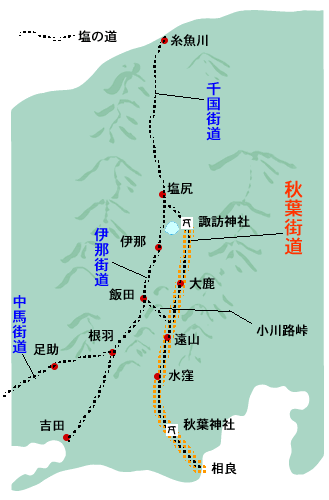 塩の道ルート
塩の道ルート
南朝皇子の戦いの道
宗良親王は後醍醐天皇の第五皇子です。
彼は比叡山の最高位である天台座主でしたが、父天皇と足利尊氏とが対立するに及んで還俗し、征東大将軍として各地を転戦しました。
一時は遠州井伊谷に身をおきましたが、興国五年(1344)に信州大河原(現大鹿村)に入り、以後37年間、この地を拠点としました。
当時の遠信古道沿線は、南朝方の豪族が勢力を保っていました。
信州の諏訪氏・香坂氏、遠州の奥山氏・天野氏・井伊氏などです。
諸氏の狭間に位置した遠山氏が南北どちらに味方していたかは明らかでありませんが、おそらくは近隣の香坂氏や奥山氏と連携していたのではないかと想像されています。
「奥山城西誌」には、後醍醐天皇の御子の”妙法院宮由機良親王”が、奥山郷(現水窪町)に行宮を建てたという伝承が記されています。
妙法院とは宗良親王の法名ですが、この人物が宗良親王のことなのか、宗良親王の御子とされる尹良親王のことなのかは定かでありません。
しかしこうした伝説が、この街道が南朝方の重要な軍用路として利用されていたことを裏付けるものであることは確かです。
 宗良親王が居を構えた大河原城(大鹿村)
宗良親王が居を構えた大河原城(大鹿村) 南朝皇子を助けた奥山氏の居城、高根城(水窪町)
南朝皇子を助けた奥山氏の居城、高根城(水窪町)
武田信玄が切り拓いた軍用路
元亀三年(1572)、信玄は遠江・三河を攻略するために軍を三方に分け、自身は小川路峠から青崩峠を越えて天野氏の犬居城に入りました。
甲府から浜松へのルートは、富士川沿いに南下する道や、伊那から新野峠を越えて後の三州街道を下る道も考えられます。
信玄があえて青崩峠越えを選んだのは、道沿いに大きな勢力がなく、遠山氏・奥山氏・天野氏を押さえれば容易に通過できるメリットがあったからでしょう。
信玄は交通路があったから進撃するのではなく、進撃のためにみずから道を押し広げたのです。
江戸時代になって秋葉街道や中馬街道が信仰路・通商路として栄えた背景には、こうした戦国大名たちの努力があるのです。
■参考文献
『南信濃村史 遠山』 昭和51年 南信濃村史編纂委員会編 南信濃村発行
関連記事
-

-
せせらぎの里で陶芸体験
せせらぎの里で陶芸体験 せせらぎの里陶芸館では、訪れた人が気軽に陶芸を体験することができます。体験できるのは、製作過程のうち成 >続きを読む
-
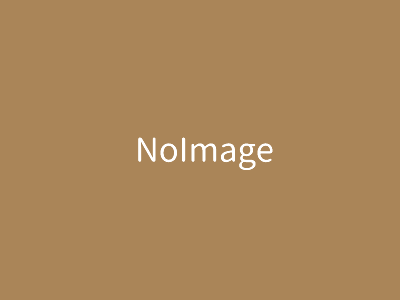
-
9月20日はバス100円
9月20日(祝)は 公共交通の日(明治36年9月20日 京都市で日本に最初にバスが走った) だそうです。 遠山郷線(飯田~和田 >続きを読む
-

-
下栗案内人の会・お申込み窓口
私達が下栗の魅力をご案内いたします にほんの里100選、日本のチロル「下栗の里」を 地元案内人がご案内いたします おすすめコース >続きを読む
-

-
南アルプスジオパーク クイズラリーin遠山郷~目指せジオ★マスター 11/20 (期間延長)
解答期間を延長しました! 2017/11/20 午後3時までに アンバマイ館へ提出してください。 web版もお楽 >続きを読む
-

-
道の駅遠山郷・セルフ焼肉
道の駅遠山郷の新名物 セルフ焼肉 道の駅遠山郷で体験できるようになりました。 詳細は、下記ホームページをご覧ください! &nbs >続きを読む
-
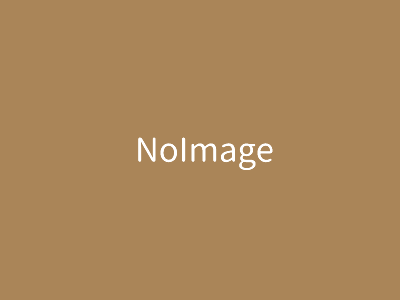
-
遠山漁協 渓流釣り開始 3/1-
遠山漁業協同組合 より例年通り 3月1日から 渓流釣り 開始しました。 主な漁場 ●本谷口 ●梶谷川(なるべく複数人で) ●池口 >続きを読む
-

-
ジオガイド研修(名古山・黒瀬川帯)のお知らせ 一般の方も参加できます。
名古山及び八重河内(黒瀬川帯)ジオガイド研修が以下の日程で開催されます。 2025年 3月2日 (日) 名古山 >続きを読む
- 前の記事
- しらびそ高原ミニ登山
- 次の記事
- 秋葉街道~現代に残る街道風景~